陳 佑真 研究室
キーワード:
漢文学、儒学、朱子学、蘇軾
 この研究室・ゼミの教員
この研究室・ゼミの教員
研究を始めたきっかけ
人間の本質とは何か、という問いが研究の出発点です。中学生の頃から古代ギリシアやドイツの哲学書を和訳で読んでいましたが、結局人間の思考は身を置いた時代や社会の文脈を離れて存在しえないと考え、大学の授業で出会った中国の考証学が古典を取り巻く世界を包括的に理解しようとしていることに惹かれて漢文学の世界に入りました。
特に、儒学の経典が普遍的な指針とされ、歴代の人々が時代に合うよう新解釈を提示する営みを面白く感じ、古典の読まれ方という観点から東洋の思想史を研究しています。

わたしの研究室
漢文学の中でも思想分野、時代でいうと宋代(960~1279)を中心に研究しています。具体的には四書五経に代表される儒家の経典を宋代の人がどう考えたのかを読み解いています。宋代には蘇軾や朱熹といった文化・思想上の巨人が多数登場し、中国はもちろん、日本にも現在に至るまで影響を与えてきました。彼らの思想的な営為を明らかにするためには原典を丹念に読み解くしかない、という考えのもと、地味ではありますが文献の読解を進めています。
ゼミ生の卒業論文のテーマは漢文学に関わるものなら思想・文学・歴史・文化などなんでも可能です。近年のものから例を挙げると、『論語』、『韓非子』、『史記』、『後漢書』、王維、古典小説中の豪傑たち、荻生徂徠、本居宣長など多種多様です。
ゼミは輪読形式で仲間と切磋琢磨して漢文の読み方の基礎をマスターします。令和七年度は『文選』・『列女伝』を注釈とあわせて読んでいます。
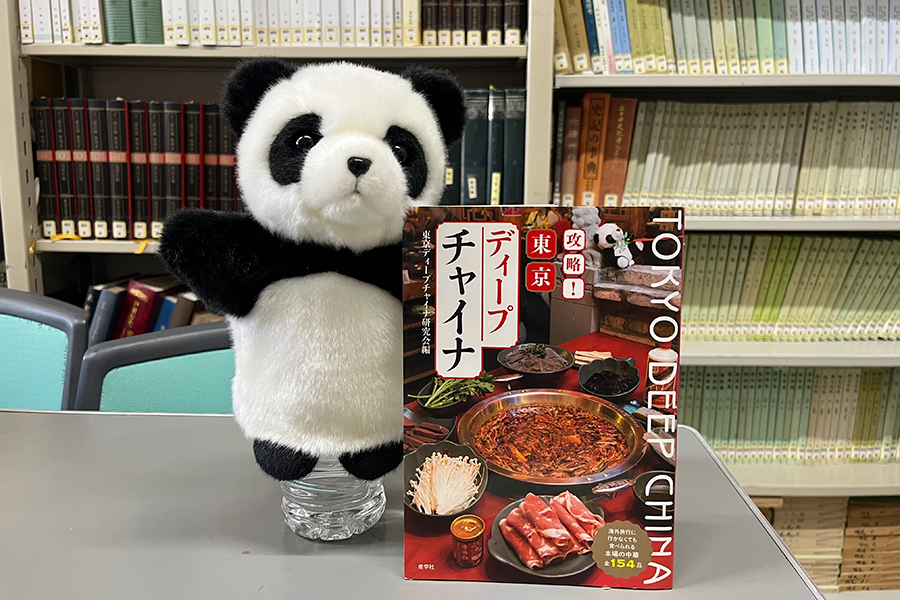
いま興味のあるテーマ
もともと蘇軾の儒学思想について研究してきましたが、最近はそれがのちの朱子学に、さらには明代・清代の学術にどのような影響を与えたのか、という観点で研究を進めています。
それ以外では近現代日本における漢文学についても以前から興味をもっております。本学とも深い関わりをもつ諸橋轍次の漢詩の訳注を『国語国文学論考』にて連載中です。また、駒澤大学との共同研究で明治時代の石川鴻斎と清の外交使節らとの応唱漢詩についても分析を進めています。
研究室インタビュー
未だ謎の多い漢文学を、解釈した先人の価値観や社会に対する考えなども考察しつつ探究
私は、儒教の経典に関する注釈学をベースに、主に中国の宋代における思想を研究しています。ゼミでは、学生の要望を聞きながら文献を選び、細かく切って担当を決め、漢文の訓読(書き下し)と現代日本語訳、注釈、作品が書かれた時代性などを調べて発表し、議論しています。こうした学びを通して、漢文学のおもしろさ、奥深さを味わうと共に、異本を比較して議論する、出典を調べて表現の源流に到達するといった漢文研究の手法を身に着け、卒業論文へとつなげていきます。


