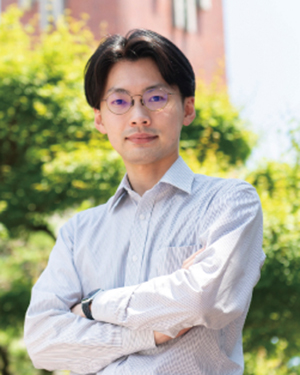堤 博一 研究室
キーワード:
言語学、英語学、生成文法、統語論、意味論
 この研究室・ゼミの教員
この研究室・ゼミの教員
研究を始めたきっかけ
小学生の頃の私は、意味のわからない歌や会話を強いられる外国語活動が苦手で、英語とは一生縁がないと思っていました。ところが中学で英語を教科として学ぶうち、語彙と文法という有限の知識をもとに無限の表現を理解し、作り出せることに感動し、世界が広がりました。大学でノーム・チョムスキー氏の生成文法というアプローチに出会ったとき、言語を論理的に扱うそのアプローチに強く惹かれ、自然と研究の道へ進むことになりました。
わたしの研究室
わたしの研究室では、生成文法を中心とした理論言語学を扱っています。英語と日本語を対照的に観察し、文法現象の普遍性や人間言語の本質に迫ることを目指しています。たとえば今年の3年ゼミでは、「非対格性」をテーマに文献講読を進め、先行研究を批判的に検討する力を養っています。ゼミでは、学生の自発性を尊重しつつも、3年次には私がある程度リードし、文献の批判的検討の仕方や、学術的な問いの立て方を指導します。4年次には、それぞれが関心に基づいた問いを掘り下げ、卒論として仕上げていきます。卒論テーマには、anyやeverのような否定極性項目の分析といった理論的研究や、日英語の結果構文の比較・対照的研究、英語の第二言語話者による英語副詞の解釈に関する実証的研究などがあります。語学の上達や教授法といった「役に立つ」トピックではなく、言語そのものと格闘するアプローチが本研究室の特色です。「当たり前」に見える言葉に疑いの目を向け、理論的にその本質を問い直す―そんな知的挑戦に惹かれる人には、刺激に満ちた場となるはずです。
いま興味のあるテーマ
現在は、固有名詞のde re解釈の統語構造と意味解釈規則に関心があります。クワインのいわゆる「ダブルビジョン問題」に接続するテーマで、生成文法の観点から、どのようにde re読みを構造的に保証できるかを検討しています。もともと数量詞のスコープ多義性を扱った博士論文に取り組んだこともあり、名詞句の解釈とスコープの問題には一貫して惹かれます。形式意味論や言語哲学の議論も参照しながら考察を進めています。