令和7年度
r7第5回 子どもを信じる学級づくり~ 教師の遊ぶ心×子どもの育つ力~
10月25日(土曜日)17時00分より、第5回「学級づくりの向上をめざす実践講座」を開催しました。今回は、和智 宏樹先生(上野原小学校教諭)を講師としてお招きしました。
当日は、県内の小中高の教員、本学学生(1年生~4年生)など10名の参加があり、「子どもを信じる学級づくり~教師の遊ぶ心×子どもの育つ力」をテーマに実施しました。
「自分をふりかえって~先輩になるために」や、「押しつけないしつけ、誰が言うか・何を言うか」、「児童とのかかわりを通して学級づくりを考える」、「信頼と安心を生み出すために」等についてペアワークや情報交換をしながら考えました。
次回は11月22日(土曜日)に開催です。事前申込なし、参加料は無料です。ぜひ、奮ってご参加ください。(対象者は山梨県内の教員、本学学生になります)
今年度はZoomでの視聴を検討しています。興味がありましたら是非ご連絡ください。
当日の様子




感想
自分の間違い、失敗を認めてアップデートしようとしたこと。本来勉強でつまずいたら何度も繰り返し試行錯誤してできるようになるはずである。指導する立場である教員がそれを放棄してはならないと感じた。(大学3年生)
・最も心に残ったのは「育つ力を信じて、遊ぶ心をもってゆっくりと」ということです。子どもの成長をすぐ見たい、早く形にしたいと思ってしまいそうですが、手助けをしながら見守り、時には助けながら、待つことの大切さを学びました。また子どもの言動を記録することでふりかえることができるので、来年からしっかり記録しようと思いました。
(大学4年生)
・先日学校でアンラーンにかかわる話をしました。先生方の多様な考えを尊重しつつも「そこまでするべきか……」と考える自分と葛藤する毎日を過ごしていました。正しい行動を認め教えること、子どもたちの心を一番に考えることを大切にしていこうと思いました。(小学校教諭)
・問題行動を起こす子にも起こした背景があり、育てている親があり、周りで見ている子があり、という背景と影響をちゃんと想像した上で声掛けをしていきたいと思いました。成果主義的にではなく、生徒や同僚に対してもっと内面的な見方をしていきたいと思いました。(中学校教諭)
第4回 学級が楽しい!~今こそコロナ禍を乗り越えた日々に学ぶ
9月27日(土曜日)17時00分より、第4回「学級づくりの向上をめざす実践講座」を開催しました。今回は、小佐野真純先生(河口湖南中学校)を講師としてお招きしました。
当日は、県内の小中高の教員、本学学生(1年生~4年生)など14名の参加があり、「学級が楽しい!~今こそコロナ禍を乗り越えた日々に学ぶ」をテーマに実施しました。
「学級担任としての葛藤-生徒に任せられない、指導しなくては。しかし踏み込めない自分」や、「生徒を信頼すること」、「コロナ禍で考えたこと」、「学級の楽しさとは…関わりとつながり(生徒同士、先輩後輩、生徒と教師)」等についてペアワークや情報交換をしながら考えました。
次回は10月25日(土曜日)に開催です。事前申込なし、参加料は無料です。ぜひ、奮ってご参加ください。(対象者は山梨県内の教員、本学学生になります)
今年度はZoomでの視聴を検討しています。興味がありましたら是非ご連絡ください。
当日の様子



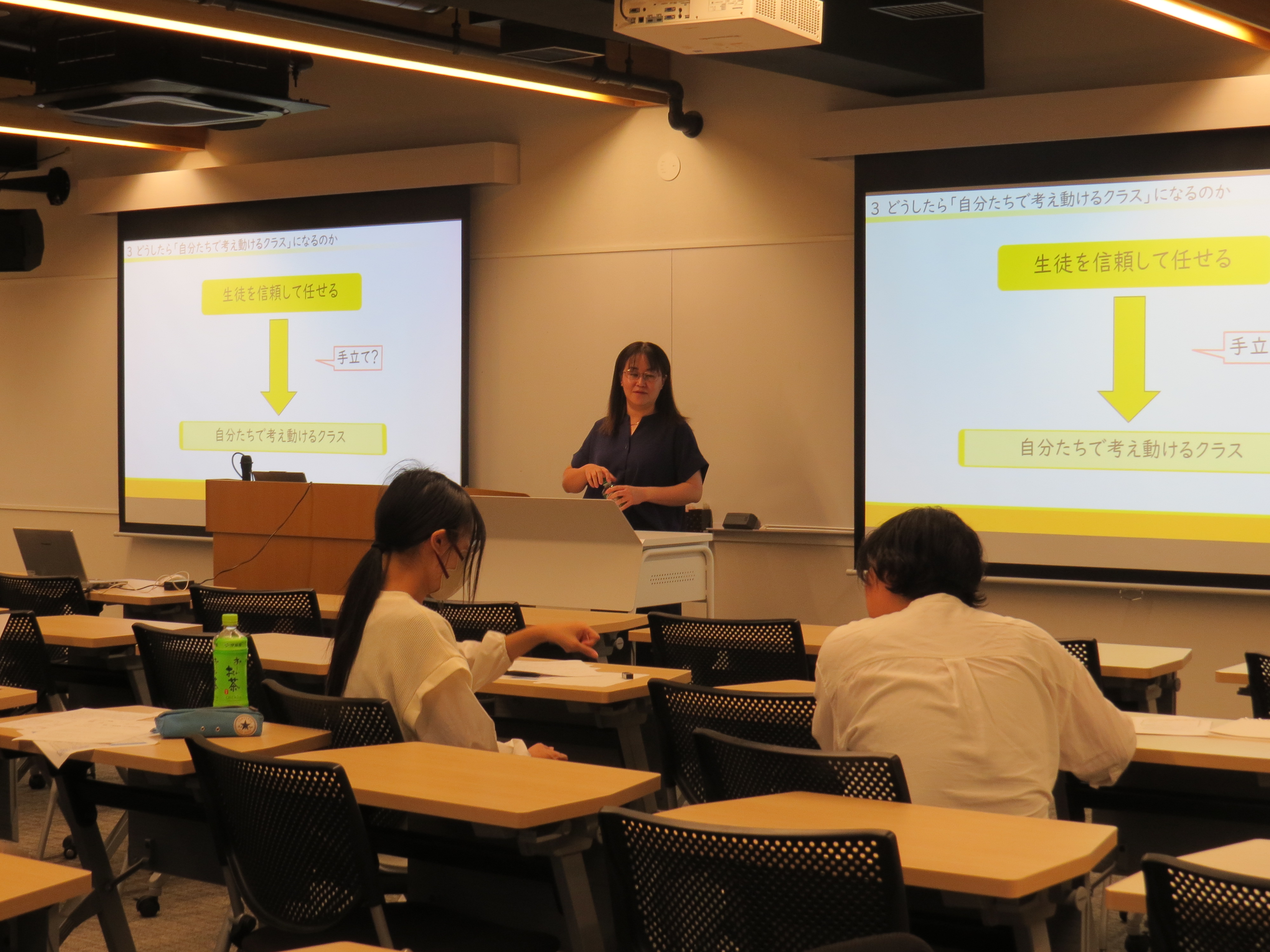
感想
原案の指導について、ものごとを全員で共有し、主体性を身につけることができるのには目を見張った。また、自身の原点が学級づくりに生かされているという話より、私も原点を振り返り、指導を行いたいと思った。(大学1年生)
「2年目の葛藤」という項からはじまったことが印象に残りました。決して簡単な道のりではなかったことを拝察することができ、自分自身も今日の講義に学んだ「自分たちで考える/話し合う/関わりをつくる/楽しみを見出す」を大切にしていきたいと思いました。( 聴講生)
・目的をもった班をつくっていくことの大切さを学びました。原案を作って提案していく流れを自分も活用していきたいと思いました。(小学校教諭)
手立ての立て方として、最初は丁寧に、そして徐々に手放していく。今日の原案資料を拝見して、自分の学級経営にも生かしていきたいと思いました。自らが関わる以外にも、自分を通して関わりを意識させるということ。義務教育の間に人とつながることの楽しさを根付かせたい。(中学校教諭)
第3回 「良い」学級を考える~子どもが安心して楽しく過ごせる学級づくり~
7月26日(土曜日)17時00分より、第3回「学級づくりの向上をめざす実践講座」を開催しました。今回は、高橋 英児先生(山梨大学教授)を講師としてお招きしました。
当日は、県内の小中高の教員、本学学生(1年生~4年生)など23名の参加があり、「「良い」学級を考える~子どもが安心して楽しく過ごせる学級づくり」をテーマに実施しました。
「改めて「学級」という場を考える…「教師の視点」と「子どもの視点」」や、「多様な関係と関わり方を学ぶ場としての「学級」」、「子どもの声から学級の活動を構想する」、「・子どもの生活をつかむ…子ども理解の視点」等についてペアワークや情報交換をしながら考えました。
次回は9月27日(土曜日)に開催です。事前申込なし、参加料は無料です。ぜひ、奮ってご参加ください。(対象者は山梨県内の教員、本学学生になります)
今年度はZoomでの視聴を検討しています。興味がありましたら是非ご連絡ください。
当日の様子




感想
講義を受けていて木村泰子さんの「困った子は困っている子」を思い出しました。子どもの要求に寄り添い、子どもと先生がともに成長していくためには生徒への信頼や聞き合いと同時に、私たち教員側の余裕や度量が重要であると学びました。(大学1年生)
・学級をつくるために、子どもたちの「声」を聞くことが大切というのが印象に残っています。最初の方で紹介されていた「こんなクラスがいいな」を決めた先生は、子どもの時に違和感なく受け止めていたことも影響しているのではと感じました。受け持つ子どもたちの声に耳を傾け続けたいと思いました。(大学3年生)
・学校現場には様々な課題があり、教師同士の人間関係を円滑にしなければ解決できないことも多いです。自分の置かれた立場を生かし、「学校の当たり前を見直す」という視点をもって、先生方に働きかけたいです。(小学校教諭)
・学級を様々な視点からとらえた。構成員である生徒の思い、願い、背景を考えていくことが重要である。そのためにも、生徒と関わる時間を確保することや、その言葉や行動が何を意味しているのかを探っていく必要がある。(中学校教諭)
第2回 小学校中学年の学級経営に挑む~個から協働への試行錯誤~
6月28日(土曜日)17時00分より、第2回「学級づくりの向上をめざす実践講座」を開催しました。今回は、須藤亮佑先生(大里小学校教諭)を講師としてお招きしました。
当日は、県内の小中高の教員、本学学生(1年生~4年生)など21名の参加があり、「小学校中学年の学級経営に挑む~個から協働への試行錯誤~」をテーマに実施しました。
「教師経験の振り返りと問題意識」や、「小学校中学年の学級経営についての考察」、「小学校3年生での実践」、「1学期:課題への向き合い」等についてペアワークや情報交換をしながら考えました。
次回は7月26日(土曜日)に開催です。事前申込なし、参加料は無料です。ぜひ、奮ってご参加ください。(対象者は山梨県内の教員、本学学生になります)
今年度はZoomでの視聴を検討しています。興味がありましたら是非ご連絡ください。
当日の様子




感想
個人の活動、グループの活動を楽しくできているというのが、とても素敵でした。自分のときには苦になることも多かったので、やり方だなあと思いました。思っている以上に子どもたち自身でできるということが理解できて、それを上手く段階を踏んで引き出せるようにしたい。(大学1年生)
常に子どもを主体として楽しい学級経営をするために行動していることに感銘を受けました。子どもに行動を定着させるには長い時間をかけなければならないので、根気強く、時には見直して変化を待つ必要性を学ぶことができました。(大学3年生)
授業づくりも学級づくりも両方大切にしながら見通しをもって指導しているところ。多様な子どもたちがいる中で、一人一人をクラスの一員として関わり合いの中で成長させている。学級づくりの大切さを実感しました。(小学校教諭)
実践内容から講義をしていただくことで、学級づくりの基盤をつくる流れが分かりやすく、自身の学級経営に活かす方法が見出せました。学級の規律(ルール)づくりが基盤にあり、その上で協働があるということを学べました。(中学校教諭)
第1回 「学級づくりの分岐点~組織する力を子供と共に伸ばすには~」
5月24日(土曜日)17時00分より、第1回「学級づくりの向上をめざす実践講座」を開催しました。1回目の今回は、渡辺幸之助先生(武蔵野大学特任教授)を講師としてお招きしました。
当日は、県内の小中高の教員、本学学生(1年生~4年生)など21名の参加があり、「学級づくりの分岐点~組織する力を子供と共に伸ばすには~」をテーマに実施しました。
「たちまち直面する壁―学級担任1年目の悩みから」や、「秩序の崩壊に一人で立ち向かう怖さ」、「学級づくりの仲間を見出す―師、友、そして子どもたち」、「学校は組織的に子どもを守り、鍛え、育てる場所」、についてペアワークや情報交換をしながら考えました。
次回は6月28日(土曜日)に開催です。事前申込なし、参加料は無料です。ぜひ、奮ってご参加ください。(対象者は山梨県内の教員、本学学生になります)
今年度はZoomでの視聴を検討しています。興味がありましたら是非ご連絡ください。
当日の様子




感想
今の時代は集団よりも個人の方に重きを置かれるような感じがしていたけど、心理的安全性を得るためにはやっぱり組織が大切だと思いました。組織をつくりあげるのは難しいことだけど、生徒一人一人としっかり向き合い生徒・先生間で意思疎通し合える学級は素敵だと思いました。(大学1年生)
学級づくりをする上で「個人的なことは政治的なこと」ということを大事にしていきたいと思いました。クラス内で思っていることや不満は、クラスの8割くらいが感じていることだと思うので、子ども一人一人と向き合い、声に耳を傾け、心理的安全性を保てる学級にしたいです。(大学4年)
「組織」という言葉で最初にウェビングをしたとき、講師が「心強い」とあげていてすごく納得しました。1年目の大変な時期を思い出しました。同時に今所属している組織は素晴らしく恵まれているのだなと改めて実感しました。(中学校教員)
このような学びの場があることを大変ありがたく思います。子どもたちが活動を通して得るものが、仲間がいる心強さ、主体的に学びたい気持ちを育めるものにしたいと思いました。教員集団としても安心してやり取りできる、心強いと思えるつながりをつくっていける存在になりたい。(聾学校教員)
