 このシーズの研究者
このシーズの研究者
 台湾・国立政治大学原住民族研究中心提供
台湾・国立政治大学原住民族研究中心提供
ヤマモト ヨシミ
山本 芳美
YAMAMOTO Yoshimi
教養学部 比較文化学科 教授
研究を始めたきっかけ
学部生時代に、文化人類学のゼミに所属したところ、「身体の文化的行為」について調べることになりました。大学図書館にある書籍や雑誌論文を読み漁ったところ、イレズミをはじめとする身体加工行為について興味をもつようにななりました。ただし、自分でも何となくこのテーマを選ぶのは怖かったので、1990年2月ごろに指導教官に相談したところ、「ハイハイ、あなたはこのテーマで卒論を書きなさい」と非常に面倒くさそうに言われたのを覚えています。そのあと30年以上、このテーマに関連した研究をするとは思いもよりませんでしたが、結果的には良かったかと。
研究概要
世界の各社会でおこなわれている身体加工行為について研究をしています。特に研究してきたのはイレズミです。90年代はじめに沖縄全域で、女性が慣習的におこなってきたハジチと呼ばれる手のイレズミについて聞き書きをして修士論文を書きました。90年代後半からは台湾の先住民族(台湾原住民族)のタイヤルの人々のイレズミについて調査をおこない、学位論文を提出しました。以後、19世紀末に東南アジアや欧米で活動した日本人彫師や、映画やテレビドラマのために刺青を描いてきた刺青絵師に関する研究をおこなってきました。最近は、沖縄の各米軍基地周辺で発展してきたタトゥー業についての聞き取り調査をしています。化粧に関しても、20年ほど化粧文化研究者ネットワークという研究会で世話人として活動してきました。
ほかに、力を入れて来たのは、日本統治期における台湾原住民族の歴史研究です。代表的研究は、征台の役で東京に連れて来られたパイワンの少女オタイさんの研究です。台湾文学研究者の倉本知明さんによる『フォルモサ南方奇譚』(2024年、春秋社)で取り上げていただいたほか、国立台湾歴史博物館では2023年にオタイさんの体験がVR化されています。
連携できるポイント
長年、沖縄や台湾で調査活動をしてきたので、中高生の修学旅行の訪問先や学習のポイントについてアドバイスができます。
資料・情報調査に関して、何をどう調べたらよいのかについてお手伝いができます。
提供できるシーズまたは支援できる分野
企業内で活動してきた人々、特に職人へのライフヒストリーの聞き書き。社史などの記録の作成など。
社会的成果または実用化された内容、商品、特許など
提供できるシーズまたは支援できる分野の例として、東映京都撮影所を拠点として俳優・刺青絵師として活動されてきた毛利清二氏(1930年生まれ)への聞き書きをまとめた『刺青絵師 毛利清二:刺青部屋から覗いた日本映画秘史』(原田麻衣との共著、2025年、青土社)があります。また、皮革産業資料館の副館長であった稲川實氏との共著で、『靴づくりの文化史:日本の靴と職人』(2011年、現代書館)も刊行しています。
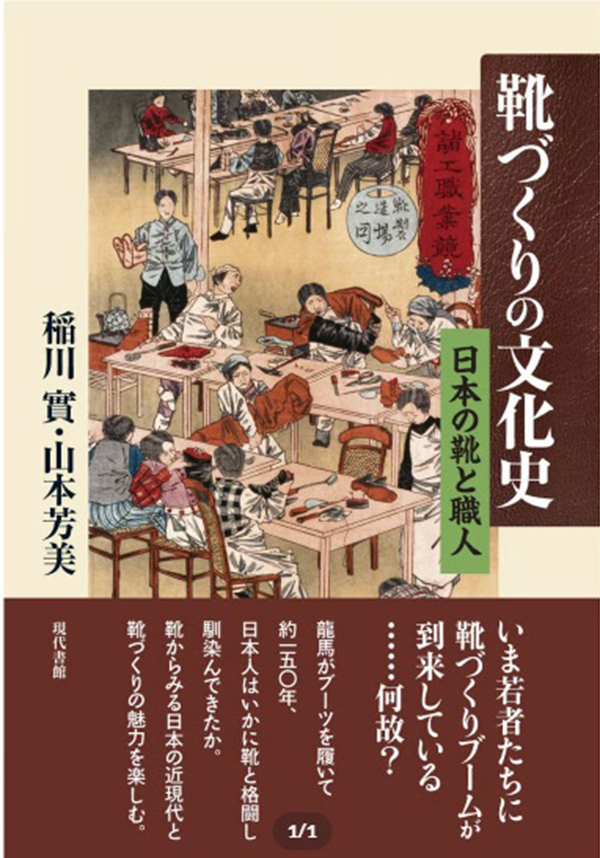
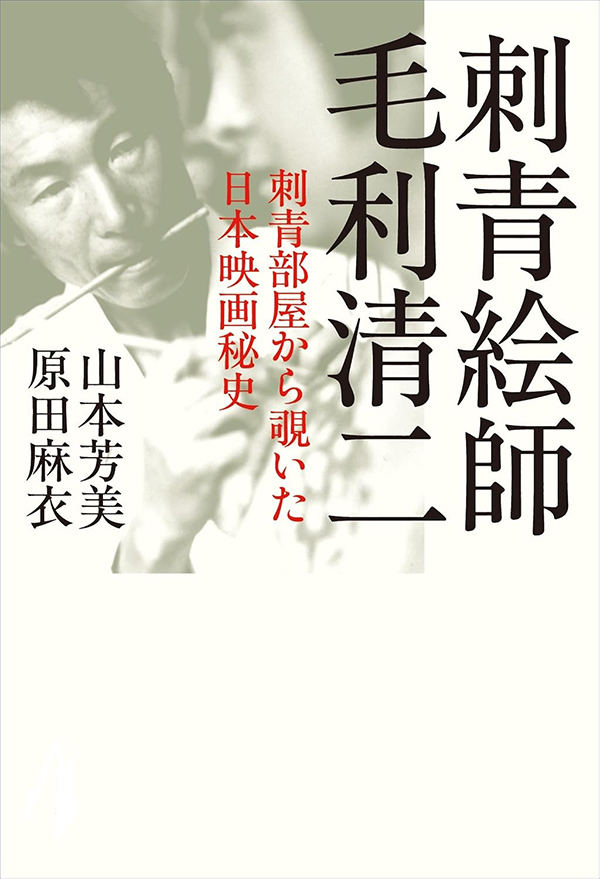
産学・地域貢献に関する経験・実例及び連携できる団体
沖縄の企業である株式会社Nanseiと共同で、2019年10月に沖縄県立博物館・美術館において『沖縄のハジチ、台湾原住民族のタトゥー:歴史と今』展を監修しました。コレクションを提供し、解説を執筆しました。本展は、これまでに沖縄県東村の山と水の生活博物館、海洋文化館、ユンタンザミュージアムを巡回しました。
