 このシーズの研究者
このシーズの研究者

フルヤ カズヒサ
古屋 和久
FURUYA Kazuhisa
教養学部 学校教育学科 教授
研究を始めたきっかけ
小学校・中学校の教育現場で30年近く教師をしながら考え続けてきたこと。それは、誰一人「学ぶ」ことに背を向けず・「学ぶ」ことに夢中になり、「学ぶ」ことに喜びを感じる教室をどうやってつくるかということです。そういう教室は、授業研究だけをしていても実現しません。生徒指導や学級活動だけに取り組んでいても実現しません。こうしてたどり着いたのが「学び合う教室文化づくり」という教育実践ビジョンです。

研究概要
わたしの研究室では、実践「学び合う教室文化づくり」における3つの領域(授業づくり、「ひと」・関係づくり、教室空間デザイン)に関わる実践研究に取り組んでいます。授業づくりにおいては、「対話的な学び」や「深い学び」、「教科書読み」や「教科日記」などの実践について研究しています。「ひと」・関係づくりにおいては、「話の聴き方(アクティブな聴き方)」や「わからない」を大切にする授業などについて研究しています。教室空間デザインにおいては、「教室美術館」の実践や「数学者の黒板」の実践など、教室を「学び」が生まれる豊かな空間にするための実践研究に取り組んでいます。
もう1つ、地域教材を活用した授業実践にも取り組んでいます。とくに、地域に伝承する祭りや行事・民俗芸能・伝説などの民俗文化財を取りあげた教育実践(「民俗と教育」実践)が、今とこれからの社会の中でどのような意味を持つのか考えていきたいと思っています。ゼミに所属する学生さんたちは、「学び合う教室文化づくり」の実践をベースとしながら、小さな事でも教育現場で必要とされる研究を意識しながら卒業研究に取り組んでいます。

連携できるポイント
「学び合う教室文化づくり」の実践研究のため、山梨県内の学校や愛媛県(西条市)、山形県(酒田市・山形市・遊佐町)、千葉県(八千代市)の小中学校・義務教育学校、沖縄県(那覇市)や千葉県(八千代市)等の教育研究団体と連携し研究を深めてきました。今後とも、「学び合う教室文化づくり」に関心のある学校や自治体と連携し研究を深めていきたいと考えます。
「学び合う教室文化づくり」の実践が企業経営者の関心を呼び、山梨県中小企業同友会や神奈川県中小企業同友会、栃木県中小企業同友と連携する機会を得ました。今後とも「学び合う企業文化づくり」のために役立ちたいと考えています。
民俗文化財を教材とした授業実践に取り組んできた経験を活かし、民俗文化財を活かした教育実践や「博物館と学校教育」に関心がある教師や団体と連携し、研究を深めていきたいと考えます。
提供できるシーズまたは支援できる分野
- 小中学校での「学び合う教室文化づくり」に関する授業指導と講演
- 教育委員会や教育研究団体主催の研修会での「学び合う教室文化づくり」に関する講演
- 企業関連団体の研修会等での「学び合う企業文化づくり」に関する講演
- 「博物館と学校教育」に関する実践研究での協同研究
- 「地域と教育」に関する実践研究での協同研究
- 山梨県の無形民俗文化財に関する調査研究
社会的成果または実用化された内容、商品、特許など
著作(単著)
- 『民俗と教育実践 ―伝説との出会い―』(1999 日本図書刊行会)
- 『「学び合う教室文化」をすべての教室に』(2018 世織書房)
- 『「教室の未来」を創る12の教育実践』(2024 世織書房)
著書(分担執筆)
- 『ふるさと山梨の民俗世界』(2024 アスパラ社)
- 『はじめての民俗学』(2012 ミネルヴァ書房)
- 『知って役立つ民俗学』(2015 ミネルヴァ書房) 他
テレビ番組出演
- NHK総合「クローズアップ現代 “十歳の壁”を乗り越えろ」2009
- NKK・Eテレ「ETV特集「『輝け 28の瞳』学び合い支え合う教室」2012
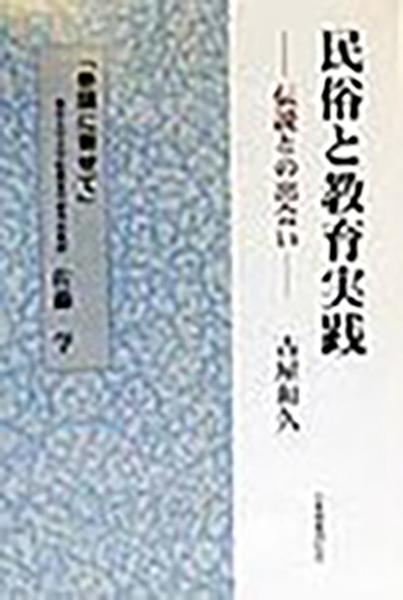
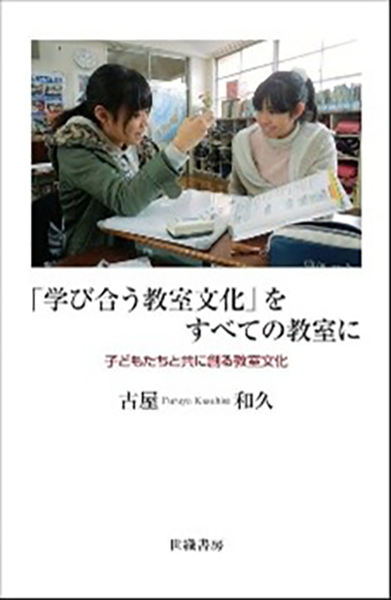
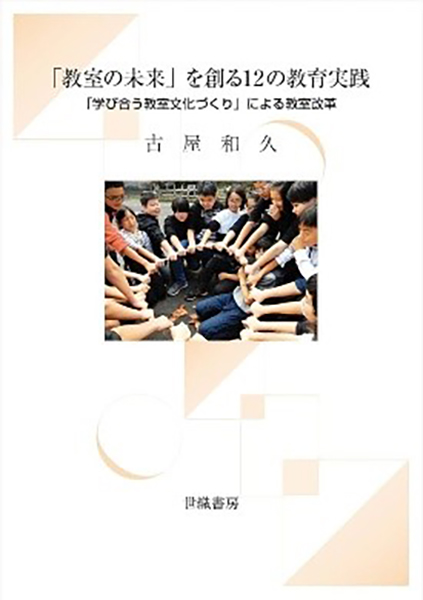
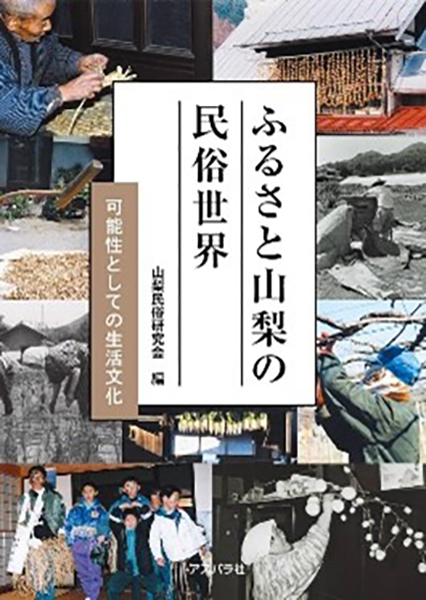
産学・地域貢献に関する経験・実例及び連携できる団体
現在以下の活動を行っています
- 山梨県文化財保護審議会委員
- 身延町文化財保護審議会委員
- 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館運営委員
