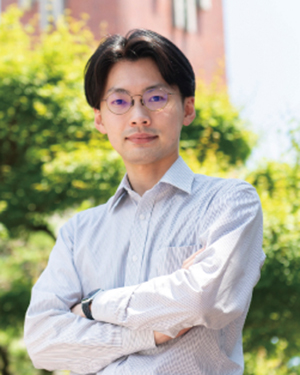このシーズの研究者
このシーズの研究者
研究を始めたきっかけ
小学生の頃、外国語活動で意味のわからない英語の歌を歌わされた経験から、英語に苦手意識を持っていました。ところが中学で文法や語彙を系統的に学ぶうちに、英語が論理的に理解・運用できる体系であることに気づき、一気に世界が拓けたように感じました。大学では生成文法に出会い、有限の語彙と規則から無限の文が生み出されるという枠組みに魅了されました。言語という身近で当たり前に思えるものに、原理的な説明を与えることの面白さに惹かれ、研究の道へと進みました。
研究概要
私たちはふだん、言葉を何気なく使っていますが、その背後には驚くほど精緻な仕組みが隠れています。現代の言語学の共通理解では、文の組み立ては、単なる語の並びではなく、人間の頭の中にある規則に従って構成されています。私は、英語や日本語の文を例にとりながら、こうした言葉の仕組みを明らかにする研究に取り組んでいます。特に関心があるのは、「ある言い方がどうして自然に感じられるのか」「別の言い方がなぜ不自然に感じられるのか」といった違いの背後にある規則です。文法や言葉の意味の成り立ちを探ることで、人間の思考や理解の仕方にも迫ることができます。言語は、単なる伝達手段ではなく、人間らしさの核心にある知的な営みだと考えています。
連携できるポイント
- 言語の仕組みに関する知見を、国語・英語教育における文法指導や読解指導に応用可能
- 「自然な文」と「不自然な文」の違いに着目した教材の開発・検討
提供できるシーズまたは支援できる分野
- 文法教育・言語教育に関する教員研修の実施
- 中高生向けの「ことばの仕組みを考える」ワークショップ等
- 言語理解・論理的思考力育成に関する講演
- 言語と論理の関係に関する普及的講義・公開講座の実施